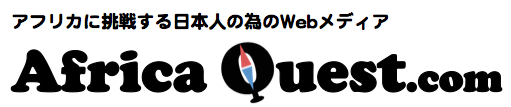日本の伝統的な医療システムである「置き薬(Okigusuri)」をアフリカの農村部に広め、家族の健康を守りながら笑顔を届ける取り組みが始まっています。
認定NPO法人AfriMedicoは「医療を通じてアフリカと日本を繋ぐ」ことをミッションに掲げ、タンザニアを拠点に置き薬の現代版を普及させています。将来的には“Okigusuri”という言葉を世界中で通じる共通語にすることを目指しています。
江戸時代の知恵がアフリカで輝く!?
日本で古くから親しまれてきた置き薬の仕組みは、必要なときにすぐ使える薬を家庭に常備し、使用分だけ後から代金を支払うという合理的なシステムです。
AfriMedicoの代表・町井氏は、青年海外協力隊として赴任したニジェールで、医療費が払えず治療を受けられない現実に直面しました。
ある母親が「子どもが高熱で危ない。病院に行くために200円貸して」と訴えてきた経験が原点です。個別に助けることも大切ですが、より多くの命を救うには社会構造を変える必要があると実感し、持続可能で実現可能な医療支援の仕組みとして、置き薬をアフリカに応用するアイデアが生まれました。
この考えは、江戸時代の日本と現在のアフリカ農村部に共通点が多いことに着目したものです。
例えば、大家族での生活や不安定な収入源、貨幣の流通が限られている点など、歴史的背景を越えて置き薬の有効性が見い出されています。町井氏の経験と洞察が、この持続可能な医療支援モデルを国境を越えて広げるきっかけとなりました。
現代の技術と融合した「アフリカ版Okigusuri」
AfriMedicoはタンザニアを中心に、現代のテクノロジーを活用した「アフリカ版置き薬」の導入を進めています。
薬箱は定期的に地域スタッフが訪問して補充を行い、使用分は後払いで精算するという仕組みです。さらに、スマートフォンを活用した支払い機能や薬品管理のアプリを取り入れることで、より多くの家庭が簡便に利用できるよう工夫されています。
この仕組みは、病院まで数時間かかるような遠隔地に住む人々にとって、命を守る大きな助けとなります。
また、病気の初期段階で対応できる環境が整えば、重症化を防ぐことも可能です。現地ではすでに家庭や学校、職場での導入が進み、地域社会に根付いた存在になりつつあります。
タンザニアの一部の小学校では、子どもたちに「具合が悪いときに何が自分を笑顔にしてくれるか」をテーマに絵を描いてもらう活動が行われ、その中で「Okigusuri box」を描いた児童もいました。これは、家族の誰かが病気のときにその薬箱が助けになっていることを示すエピソードであり、まさに置き薬が健康と笑顔を届けている証しです。
子どもたちの声が家族と地域を動かす!
学校での活動がきっかけで、「自分の家にも置き薬を置いてほしい」と親に頼んだ子どもも現れました。
小学校で絵を書いた子どもたちや置き薬の仕組みを学んだ子どもたちは、それを家庭に持ち帰り、自らの言葉で親に伝えるという流れが自然に生まれています。このように、子どもたちが家族や地域に医療への意識を広める橋渡しとなっているのです。
さらに、子どもたちが描いた絵をもとに作られた絆創膏も家庭内で使用され、活動の象徴として親しまれています。このような取り組みは、医療支援にとどまらず、教育や家庭でのコミュニケーション促進にも寄与しています。
AfriMedicoは現在、置き薬の仕組みと“Okigusuri”という言葉を、アフリカだけでなく世界各国へ広めるための活動を継続しています。
夜中でも病院に行けない、休日に薬が手に入らないといった課題を解決する手段として、“Okigusuri”が共通語になる未来を目指しています。
- 記事提供元:「置き薬 Okigusuri」を世界共通語に!日本発祥の仕組みをアフリカに広め、健康と笑顔を届けたい。|PR TIMES