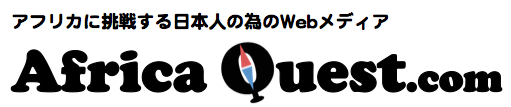東京工芸大学芸術学部は、2025年3月2日(日)から3月23日(日)まで、中野キャンパスのギャラリー6B01にて「レジリエント・ライフ:強制撤去からの帰還と再建」展を開催しています。
本展は、ケニア・ナイロビのムクル・クワ・ンジェンガ地区で強制撤去を受けた住民たちが、自らの手で住居を再建する過程を、多様な学問的視点を通して記録・展示するものです。
展示は「Materiality of Lives」と「Rebuilding Home and Dignity」の2つのプロジェクトで構成され、住民の生活と復興の姿をアートとして提示します。さらに、会期中には関連するトークイベントが開催され、都市政策や人権問題についての議論が深められます。
ケニアの強制撤去と住民の再建をアートで記録
本展は、ケニアのムクル・クワ・ンジェンガ地区における住民の生活再建をテーマに、芸術、人類学、建築学、政治学といった多様な視点で構成されています。
ムクル・クワ・ンジェンガは、ナイロビのインフォーマル居住区のひとつであり、急速な都市開発の影響を受け、多くの住民が強制撤去に直面しています。本プロジェクトでは、強制撤去を受けた住民が元の土地に戻り、家を再建する過程を記録し、その創造力と回復力をアートとして表現します。
展示の一つである「Materiality of Lives」では、住民が自力で再建した4つの家屋の壁や屋根の材料を住民の承諾のもと収集し、展示空間で再構成します。
これにより、住民がどのような資材を用い、どのように家を再建したかを具体的に可視化し、住環境の厳しさや創意工夫を伝えます。また、住民の誇りとクリエイティビティに焦点を当て、強制撤去後の生活がどのように形成されるかを読み解く試みでもあります。
もう一つの展示「Rebuilding Home and Dignity」では、住民の体験を映像作品としてまとめ、360度パノラマ写真による体験型インスタレーションを通じて紹介します。
これにより、鑑賞者は住居の内外を自由に探索しながら、住民の語りを直接視聴できる仕組みになっています。住民がどのような経緯で再建を進めたのか、どのような困難を乗り越えたのかを時系列で追体験できる貴重な機会となります。
トークイベントで都市政策や人権問題を議論
本展の開催に合わせて、都市政策や人権問題についての議論を深めるため、2回のトークイベントが企画されています。これらのイベントでは、専門家やプロジェクトメンバーが登壇し、強制撤去の影響や住民の対応、さらには日本の震災復興や都市再生との共鳴について議論が交わされます。
第1回目のトークイベント「人と住まい:強制撤去からの再建」は、3月8日(土)15:00~17:00に開催されました。文化人類学者で映像人類学を専門とする村津 蘭氏や、アーティストの西尾 美也氏をゲストに迎え、強制撤去を経験した住民たちがどのように再建を進めたのか、そのプロセスを考察します。また、住民自身の声をアートとしてどのように記録・発信するべきかについても議論がなされました。
第2回目のトークイベント「住まいと都市政策:インフォーマル居住区が映し出す社会課題」は、3月22日(土)15:00~17:00に開催予定です。ゲストとして、都市工学を専門とする小野 悠氏と文化人類学者の溝口 大助氏が登壇し、強制撤去と都市開発の関係、インフォーマル居住区の存在が示す社会構造の課題について議論を深めます。都市計画や社会的公正の観点から、持続可能な住環境のあり方についての考察が行われる予定です。
多分野の研究者による共同研究の成果
本展は、複数の大学の研究者による共同研究の成果として実現しました。東京工芸大学の野口 靖教授(インタラクティブメディア学科)、東京外国語大学の椎野 若菜准教授(アジア・アフリカ言語文化研究所)、日本女子大学の井本 佐保里准教授(建築デザイン学科)、上智大学のキティンジ・キニュア研究員(アジア文化研究所)が中心となり、それぞれの専門分野の視点を持ち寄って研究を進めています。
野口教授は、アートと社会課題の関係に焦点を当て、参加型インスタレーションを通じて社会のあり方を問い直す作品を制作してきました。椎野准教授は、東アフリカの民族誌を専門とし、ジェンダーや家族・親族の視点から研究を行っています。
井本准教授は、ケニアでのフィールドワークを10年以上継続し、住居の再建プロジェクトに関与してきました。キティンジ研究員は、アフリカ社会の貧困問題を専門とし、地域社会の発展について研究しています。
これらの研究者の協力によって、本展は単なるアート展示にとどまらず、強制撤去という社会問題を多角的に分析し、その影響と住民の対応を包括的に伝える試みとなっています。